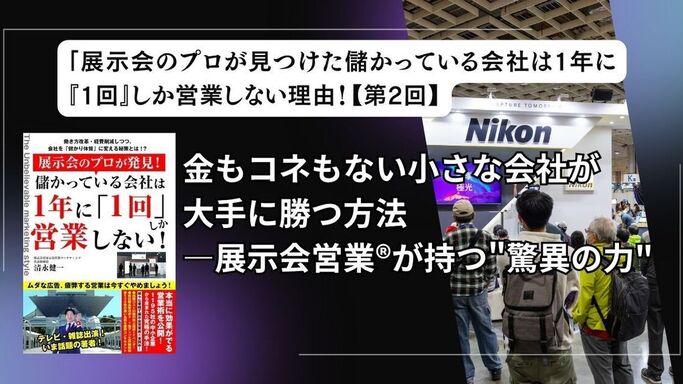中小企業の営業課題と展示会の可能性
中小企業の多くは「営業力の弱さ」に悩んでいます。
「大手のような営業部隊がない」「知名度が低く、アポイントが取りづらい」「営業経験の豊富な人材が不足している」
――こうした悩みは、多くの経営者や営業責任者にとって切実なものでしょう。しかし、本書『展示会のプロが見つけた 儲かっている会社は1年に「1回」しか営業しない理由!』の著者・清永健一氏は、そんな中小企業だからこそ、展示会営業®が効果を発揮すると説きます。
展示会という「特別な場」では、企業規模や知名度に関係なく、すべての出展者が対等に見込み客と出会えるチャンスがあります。なぜ、展示会という場は、中小企業に「驚異の力」をもたらすのでしょうか?
展示会が持つ「場の力」――中小企業の弱みを一気に解消する魔法
展示会には、中小企業の営業における弱みを一気に解消する「場の力」があります。その力は主に5つの側面から説明できます。
まず第一に、「信頼性の担保」です。一般的に、知名度の低い中小企業が新規顧客にアプローチする際、最初の壁となるのが「この会社は信頼できるのか?」という疑念です。しかし、展示会に出展しているという事実自体が、一定の信頼性を担保します。
第二に、「対等な立場での商談」が可能になります。通常の営業活動では、知名度の低い中小企業が大手企業にアプローチする際、どうしても「お願いする側」という弱い立場になりがちです。しかし、展示会では、来場者が自ら関心を持って足を運んでくるため、より対等な立場での商談が実現します。
第三に、「情報収集の効率化」です。展示会は、業界の最新トレンドや競合情報を一度に収集できる絶好の機会です。
第四に、「ブランディング効果」があります。
第五に、「人材育成の場」としての価値も重要です。
清永氏は「展示会は中小企業にとって、最も費用対効果の高い営業活動である」と断言しています。

「1年に1回」の集中投資がもたらす驚きの効果
「1年に1回しか営業しない」という本書のタイトルは、一見すると極端に思えるかもしれません。しかし、清永氏が提唱するのは、「営業活動をしない」ということではなく、「最も効果的な営業活動に経営資源を集中投資する」という考え方です。その核心となるのが、「1年に1回の展示会」への集中投資です。
なぜ「1年に1回」なのでしょうか。清永氏の調査によれば、多くの中小企業は限られた予算で複数の小規模展示会に出展する傾向がありますが、実はそれが「中途半端な結果」を生む原因になっています。例えば、年間100万円の展示会予算を持つ企業が、20万円×5回の小規模展示会に出展するよりも、100万円を1回の主要展示会に集中投資した方が、はるかに大きな成果を得られるというデータがあります。
集中投資がもたらす効果は、「準備の質の向上」「社内の一体感の醸成」「フォローの徹底」など多岐にわたります。清永氏は「展示会の成果の8割は、展示会後のフォローで決まる」と強調しています。

「展示会営業®」成功の3つの鍵――準備・実行・フォロー
展示会営業®で成果を上げるためには、「準備」「実行」「フォロー」の3つのフェーズを徹底することが重要です。清永氏は、この3つのフェーズそれぞれに「成功の鍵」があると説きます。
【準備フェーズの鍵】
展示会の成功は、準備段階で8割が決まると言われています。特に重要なのが「ターゲットの明確化」です。「誰に、何を、どのように伝えるか」を明確にしないまま展示会に臨むと、ブースデザインもプレゼンテーションも中途半端になってしまいます。また、事前告知も重要です。
【実行フェーズの鍵】
展示会当日の成功の鍵は「ブース運営の効率化」と「商談の質の向上」です。多くの企業が陥りがちな失敗は、ブースに立つスタッフの役割分担が不明確なことです。また、商談の質を高めるためには、「ヒアリングシート」の活用が効果的です。
【フォローフェーズの鍵】
展示会の真の成果は、展示会後のフォローで決まります。フォロー成功の鍵は「スピード」と「継続性」です。展示会終了後、できるだけ早く初回コンタクトを取ることが重要です。
清永氏は「展示会の成果を最大化するためには、この3つのフェーズをバランスよく強化することが重要」と説きます。

事例に学ぶ――展示会営業®で売上を倍増させた中小企業の戦略
清永氏がコンサルティングした企業の中から、展示会営業®で大きな成果を上げた事例を紹介します。
【事例】
従業員20名の町工場が大手自動車メーカーと取引開始 東京都内の金属加工を専門とする従業員20名の町工場A社は、長年下請け仕事が中心で、直接取引の開拓に苦戦していました。清永氏のアドバイスで、業界最大の展示会に出展することを決断。限られた予算の中で、独自の精密加工技術を効果的にアピールするため、「見て、触れて、体験できる」展示物を工夫しました。
特に効果的だったのは、来場者が自ら加工精度を確認できる「精度チェックコーナー」の設置です。これにより、大手自動車メーカーの技術者の目に留まり、展示会後に技術評価のための訪問が実現。その後の丁寧なフォローにより、半年後には試作品の発注を獲得し、現在では大手自動車メーカー2社との直接取引を実現。売上は展示会出展前と比較して2.3倍に成長しました。
A社の社長は「展示会がなければ、大手メーカーの門戸を叩くことすら難しかった。展示会という場があったからこそ、技術力で勝負するチャンスを得られた」と語っています。

展示会営業®で「儲かり体質」を作る――小さな会社の大きな挑戦
展示会営業®は、単に「展示会に出展する」ということではなく、企業の営業体制そのものを変革し、「儲かり体質」を構築するための戦略です。清永氏は、展示会営業®を通じて中小企業が「儲かり体質」を構築するための5つのステップを提案しています。
【ステップ1:営業活動の「選択と集中」】
限られたリソースを持つ中小企業にとって、あらゆる営業活動に手を広げることは得策ではありません。最も効果の高い活動に経営資源を集中投下することが重要です。
【ステップ2:「見込み客データベース」の構築】
展示会で獲得した見込み客情報は、企業の貴重な資産です。これらの情報を体系的に管理し、活用するための「見込み客データベース」の構築が必要です。
【ステップ3:「営業の仕組み化」】
中小企業の営業活動は、しばしば「営業担当者の個人技」に依存しがちです。展示会営業®を通じて営業プロセスを標準化し、個人の能力に依存しない営業体制を構築しましょう。
【ステップ4:「顧客との関係構築」の強化】
展示会は、新規顧客との出会いの場であると同時に、既存顧客との関係を深める機会でもあります。
【ステップ5:「PDCAサイクル」の確立】
展示会営業®の効果を最大化するためには、継続的な改善が不可欠です。
清永氏は「展示会営業®は、一度の成功で終わるものではなく、継続的な改善によって効果が倍増する」と強調しています。
次回は「展示会営業®で得られる具体的なメリットと成功事例」を詳しく解説します。展示会営業®を実践して売上を3倍に伸ばした企業の秘訣とは?本書には、すぐに実践できる具体的なノウハウが満載です。