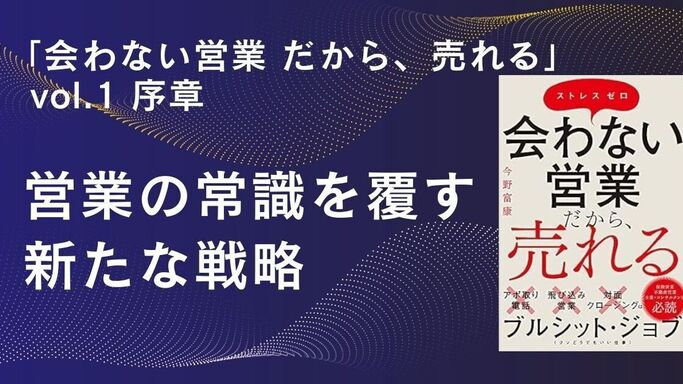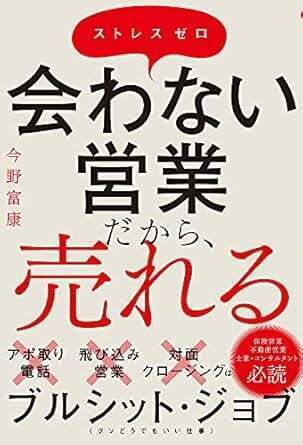営業の常識が通用しない時代へ:なぜ「会えない」のか?
現代のビジネス環境において、顧客とのアポイントメント獲得は年々困難になっています。かつては「営業は会ってなんぼ」と言われた時代もありましたが、もはやその常識は通用しません。では、なぜ顧客は私たちに会ってくれなくなったのでしょうか?その背景には、社会全体の「生産性」に対する意識の変化が大きく影響しています。長時間労働への批判が高まり、いかに少ない時間で最大限の成果を出すかが問われるようになった結果、企業は従業員の時間の使い方をより厳しく見極めるようになりました。
この変化は、営業パーソンが顧客に会うことのハードルを著しく上げています。顧客は不必要な面談を避け、自身の業務に直結しない営業活動に対しては、以前にも増して厳しい目を向けるようになりました。結果として、いくら「会いたい」と願っても、顧客のスケジュールや意向がそれを許さない、という現実が目の前に立ちはだかっているのです。
これは、従来の営業手法に固執する限り、多くの営業パーソンにとって「無理ゲー」とも言える状況を生み出しています。実際に、多くの営業パーソンが「アポイントが取れない」「商談に進めない」という悩みを抱え、成果を出せずに苦しんでいます。このような状況下で、従来の「足で稼ぐ」「とにかく会う」という営業スタイルを続けても、疲弊するばかりで具体的な成果には繋がりにくいのが現状です。

著者が「会わない営業」に至った背景:常識への疑問から生まれた革新
このような厳しい時代の中で、今野氏が提唱する「会わない営業」という考え方は、まさに既存の営業常識へのアンチテーゼと言えるでしょう。今野氏自身も長年、営業の最前線で「会うこと」の重要性を信じてきました。
しかし、顧客が会ってくれないという現実に直面し、従来のやり方では限界があることを痛感したそうです。この実体験こそが、本書が生まれた大きな原動力となっています。営業としてのキャリアの中で、様々な成功と失敗を経験し、その中で得た教訓が、この「会わない営業」という独自のメソッドの土台を築き上げました。
顧客との接点が希薄になる中で、どのようにして信頼関係を構築し、購買意欲を高めていくのか。今野氏は、J-POPの歌詞にあるような「会えない時間が愛を深める」というロマンチックな状況が、ビジネスにおいてはほとんどあり得ないという厳しい現実を突きつけます。ある統計によると、遠距離恋愛の破局率は78%にも上ると言われています。恋愛ですら会えない時間が関係を希薄にするのですから、ビジネスの世界ではなおさらです。
顧客は忘れっぽく、関係が希薄になればなるほど、やがて忘れ去られてしまうでしょう。この危機感こそが、今野氏に「会わない」という新たなアプローチを模索させるきっかけとなりました。会えない状況下で、いかにして顧客との関係性を維持し、深めていくか。この問いに対する答えを探求する過程で、「会わない営業」の骨子が形成されていったのです。

「会わない」からこそ深まる顧客との関係性:情報戦略の重要性
「会わない営業」は、単に顧客に会わない、という意味ではありません。むしろ、会わないからこそ、これまで以上に顧客との関係性を深く、そして戦略的に構築していく必要性を説いています。本書では、オンラインツールやデジタルコンテンツを駆使し、顧客が「ああ、これは自分が必要としているものだ」と自ら気づくようなアプローチの重要性が強調されています。これは、顧客が情報収集をしている際に営業担当者がどう関わるべきかの答えです。
従来の営業では、対面でのコミュニケーションに重きを置くあまり、顧客の真のニーズを見落としてしまうケースも少なくありませんでした。しかし、「会わない営業」では、顧客の多様なニーズを類型化し、それぞれのニーズに合致した情報を提供することで、顧客の購買意欲を自然に高めていく手法を提案しています。
例えば、顧客が抱える課題が明確であれば、その課題に対する解決策を提示する情報を提供します。もし顧客が漠然とした不安を抱えているのであれば、その不安を具体化し、解決の糸口を示す情報を提供するといった具合です。これは、限られた時間の中で、いかに効率的かつ効果的に顧客にアプローチするかという、現代の営業に求められる本質的な課題への解答と言えるでしょう。
顧客が自ら情報を求め、自ら購買へと動くような「仕掛け」を作ることが、「会わない営業」の核心部分を担っています。

「会わない営業」がもたらす新しい営業の形と著者からのメッセージ:顧客主導の購買体験を創出する
今野氏が本書で伝えたいのは、決して営業が不要になるということではありません。むしろ、これからの時代に求められる、より洗練された営業の形を提示しています。
顧客に「会わない」という選択は、営業パーソンに新たな思考と戦略を促します。それは、顧客の潜在的なニーズを掘り起こし、適切なタイミングで最適な情報を提供することで、顧客自らが購買へと動くような仕組みを構築するということです。これは、顧客が主体的に購買意思決定を行う、いわゆる「顧客主導の購買体験」を創出することに他なりません。
本書は、単なるテクニック集ではありません。営業を取り巻く環境が激変する中で、いかにして成果を出し続けるかという、営業パーソンにとって喫緊の課題に対する哲学と具体的な指針を示しています。今野氏の豊富な経験と深い洞察から生まれた「会わない営業」の概念は、まさに現代の営業が直面する課題を打破するための、強力な武器となるはずです。
営業の未来は、顧客との関係性を再定義し、情報戦略を駆使することで、これまで以上の成果を生み出す可能性を秘めています。本書を通じて、読者は新しい営業のあり方を学び、自身の営業スタイルをアップデートするための具体的なヒントを得られるでしょう。

成功事例に学ぶ「会わない営業」の実践力:オンラインでの集客と成果
今野氏が提唱する「会わない営業」の有効性は、数々の成功事例によって裏付けられています。例えば、今野氏は、この「会わない営業」のシナリオ設計の考え方を用いて、5000人以上を集客した大規模なイベントの事例を挙げています。
このイベントでは、集客期間を21日間と設定し、それを3日ごとに7つのパートに分割してシナリオを設計しました。最初の3通のメールで「ニーズに気づいてもらう」「ニーズを強調し、購入意欲を高める」「購入・申し込みを促す」という基本的な流れを構築し、その後も同様のプロセスを繰り返しながら、顧客の多様なニーズに対応していきました。
このように、顧客のニーズを類型化し、それぞれのニーズに合わせた情報を提供することで、顧客は「ああ、これは自分が必要としているものだ」と強く感じ、購買意欲を高めていきます。オンラインでの情報提供を通じて、顧客が自ら購買へと動くような仕組みを作り出すことが、「会わない営業」の真骨頂と言えるでしょう。これは、単に時間やコストを削減するだけでなく、顧客の購買体験を向上させ、長期的な信頼関係を築く上でも極めて有効なアプローチです。
本書を読めば、こうした具体的な実践例や、その裏側にある緻密な戦略を知ることができます。

次回予告:顧客の心を掴む「シナリオ設計」の秘密
第2回では、本書の核となる考え方の一つである「シナリオ設計」について深掘りしていきます。なぜ、顧客の多様なニーズに対応するために、詳細なシナリオ設計が必要なのか?そして、そのシナリオが、いかにして顧客の購買意欲を段階的に高めていくのか?
具体的な事例を交えながら、「会わない営業」の真髄に迫ります。この考え方をマスターすれば、あなたの営業活動は劇的に変化するでしょう。