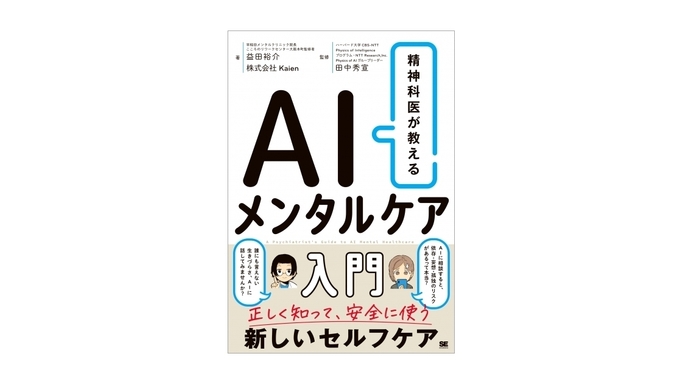「誰にも言えないモヤモヤを、AIになら話せるかもしれない」
生成AIが急速に普及する現代、AIを単なる作業効率化のツールとしてだけでなく、心の悩みを聞いてくれる「相談相手」として利用する人が増えています。しかし、そこには新たな可能性とともに、依存や孤立といった見過ごせないリスクも潜んでいます。
株式会社翔泳社は、2025年11月17日(月)に新刊『精神科医が教える AIメンタルケア入門』(著:益田 裕介、株式会社Kaien/監修:田中 秀宣)を発売しました。本書は、精神科医の視点からAIを用いたセルフケアの正しい方法と注意点を説く、現代人必読の一冊です。
なぜ今、「AIメンタルケア」なのか?
悩みや愚痴を人に話すことは、メンタルヘルスの維持において非常に重要です。しかし、対人関係の煩わしさや、「こんなことを言ったらどう思われるか」という不安から、本音を吐き出せない人は少なくありません。
そこで注目されているのが、ChatGPTやGeminiといった「生成AI」です。AIは24時間365日、文句も言わずに話を聞いてくれます。感情の整理、新しい視点の獲得、あるいはコミュニケーションの練習相手として、AIは非常に優秀なパートナーになり得ます。
本書では、こうしたAI活用の「メリット」を最大限に引き出しつつ、同時に潜む「デメリット」にどう対処すべきかを具体的に解説しています。
AI依存や「エコーチェンバー」のリスク
AIはユーザーが好む回答を生成する傾向があります。そのため、心地よい言葉ばかりを浴び続けることで、現実の人間関係よりもAIを優先してしまう「依存」や、偏った考えが増幅される「エコーチェンバー現象(妄想の強化)」に陥る危険性があります。
本書の著者であり、YouTubeチャンネル登録者数69.5万人(※発売時点)を誇る精神科医・益田裕介氏は、こうしたリスクを医学的な見地から分析。AIに相談してよいことと、相談しても解決しないこと(正解のない問いなど)を明確にし、安全な距離感を保つための指針を示しています。
「答え」が出ない時のための「パーソナル哲学」
本書の興味深い点は、AIが苦手とする領域、例えば「トロッコ問題」のような倫理的ジレンマや、個人の生き方に関わる決断について、どう向き合うべきかを掘り下げている点です。
AIはあくまで補助ツールであり、最終的な決断を下すのは人間自身です。本書では、AIを活用しながらも、自分なりの納得解を導き出すための「パーソナル哲学」の重要性を説いています。目指すゴールは、困難な状況でも「仕方がない」と受容し、「生まれてきてよかった」と思える境地です。
著者・監修者について
著者の益田裕介氏は、早稲田メンタルクリニック院長でありながら、精神疾患やメンタルヘルスに関する情報をYouTubeで発信し続けるインフルエンサーでもあります。共著の株式会社Kaien、監修の田中秀宣氏(米NTT Research, Inc.)とともに、医療・福祉・技術の多角的な視点から執筆されています。
AIと共存する未来において、私たちの心はどうあるべきか。技術書でありながら、哲学書のような深みも併せ持つ本書は、メンタル不調を感じている方だけでなく、AIとの付き合い方を模索するすべての方におすすめの一冊です。

【取材対応。テレビや雑誌、Webメディアの人へ】 気軽にご相談して下さい。 toiawase@wasedamental.com 【2ndChです】 https://www.youtube.com/channel/UC9WXfmJQZVItKASe68--PJg
書籍情報
『精神科医が教える AIメンタルケア入門』
著者: 益田 裕介、株式会社Kaien
監修: 田中 秀宣
発売日: 2025年11月17日
定価: 2,200円(本体2,000円+税10%)
判型: A5・240ページ
発行: 株式会社翔泳社