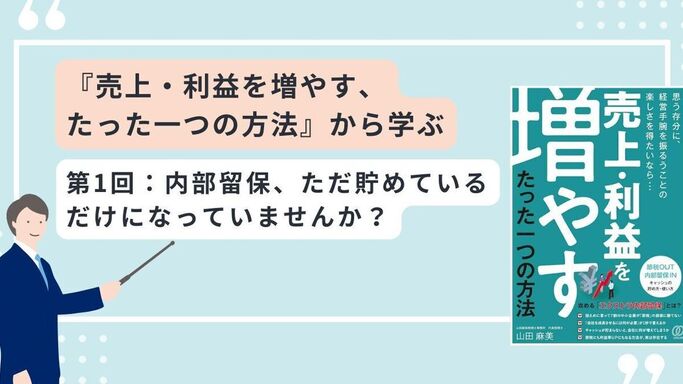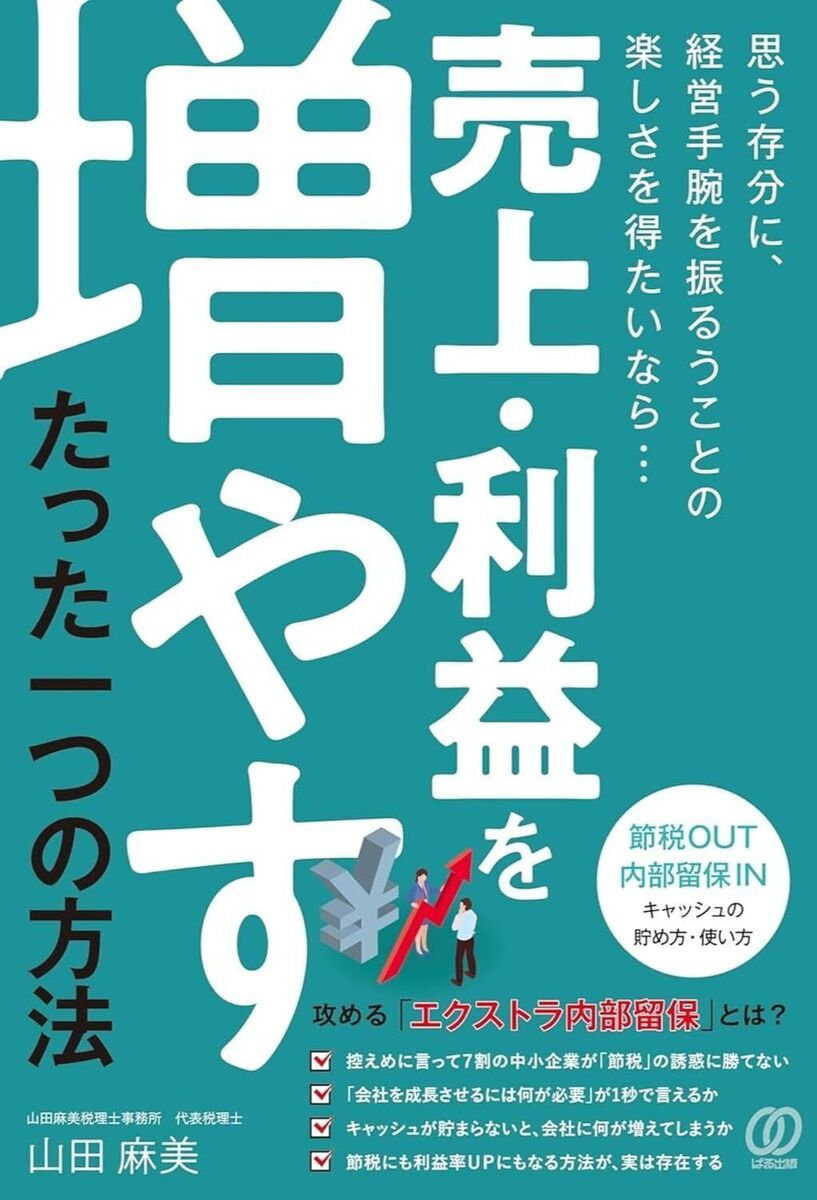内部留保、9割の会社が間違った使い方をしている!?
「会社のお金は、あればあるだけ安心」そう思っていませんか?確かに、会社の預金残高が増えるのは嬉しいものです。しかし、そのお金、ただ貯まっているだけで、本当に会社の成長に繋がっているでしょうか?多くの経営者が内部留保の活用に頭を悩ませ、間違った節税に陥っているのが現状です。

内部留保とは何か?その真の意味を考える
内部留保とは、企業活動で得た利益のうち、配当や役員報酬として分配せずに社内に留保された資金のことです。将来の投資や不測の事態への備えとして重要な役割を果たしますが、その活用方法を誤ると、会社の成長を阻害する要因にもなりかねません。
多くの中小企業経営者は、「とりあえず貯めておけば安心」という考えで内部留保を積み上げています。確かに、手元資金があることは心理的な安心感をもたらします。しかし、ただ銀行に眠らせているだけでは、インフレによる実質的な価値の目減りや、成長機会の逸失というリスクを抱えることになります。
現代のビジネス環境は変化が激しく、競合他社が新しい技術やサービスを導入する中で、自社だけが現状維持を続けていては、相対的に競争力が低下してしまいます。内部留保は「守り」の資金としてだけでなく、「攻め」の資金として戦略的に活用することが求められているのです。
間違った節税が会社を蝕む現実
「節税」と聞くと、良い響きに聞こえますが、実は間違った節税が多くの会社を蝕んでいます。例えば、必要のない設備投資や過剰な在庫を抱えることで、一時的に税金を減らすことはできても、それは会社の財務体質を悪化させる「負の節税」です。
よくある間違った節税の例として、決算期末に慌てて不要な備品を購入したり、使い道の明確でない車両を購入したりするケースがあります。これらは確かに経費として計上でき、その年の税金は減らせますが、長期的に見ると会社のキャッシュフローを圧迫し、本当に必要な投資に回せる資金を減らしてしまいます。
また、過度な節税を意識するあまり、利益を出すことを悪いことのように考えてしまう経営者も少なくありません。しかし、利益は会社の成長の源泉であり、適切に内部留保として蓄積し、戦略的に活用することで、さらなる利益を生み出すことができるのです。
税金を払うことは確かに負担ですが、それ以上に重要なのは、会社の持続的な成長と発展です。短期的な節税効果に惑わされず、長期的な視点で財務戦略を考える必要があります。

本書が生まれた背景:中小企業の成長を支援したい
著者の山田麻美氏は、税理士として200社以上の中小企業の財務状況を見てきました。そこで目の当たりにしたのは、多くの経営者が内部留保の活用に悩み、間違った節税に陥っている現状でした。「中小企業の成長を支援したい」という強い思いから、本書は誕生しました。
山田氏が特に問題視しているのは、多くの経営者が「お金を貯めること」と「お金を活用すること」のバランスを取れていない点です。安全性を重視するあまり、成長のチャンスを逃してしまったり、逆に無計画な投資で資金を浪費してしまったりするケースを数多く見てきました。
本書では、山田氏が実際に関わった企業の成功事例や失敗事例を豊富に紹介しながら、内部留保の正しい活用方法を具体的に解説しています。理論だけでなく、実践的なノウハウが詰まっているのが本書の大きな特徴です。
また、山田氏は「税理士は税金を減らすことだけが仕事ではない」という信念を持っています。真の税理士の役割は、企業の財務体質を改善し、持続的な成長を支援することだと考えており、その思いが本書の随所に表れています。

「エクストラ内部留保」という革新的な考え方
本書では、「エクストラ内部留保」という独自の考え方を提唱しています。これは、ただ漫然と内部留保を貯めるのではなく、戦略的に活用することで、さらなるキャッシュを生み出すという考え方です。
従来の内部留保の考え方は、「万が一に備えて貯めておく」という受動的なものでした。しかし、エクストラ内部留保は、「積極的に投資して、より多くのリターンを得る」という能動的なアプローチです。
具体的には、内部留保を以下のような分野に戦略的に投資することで、会社の収益力を向上させます:
• 従業員のスキルアップや教育投資
• 業務効率化のためのシステム導入
• 新商品・新サービスの開発
• マーケティングや販売促進活動
• 設備の近代化や生産性向上
これらの投資は、短期的には支出となりますが、中長期的には売上増加や コスト削減につながり、結果として内部留保をさらに増やすことができます。つまり、内部留保が内部留保を生み出すという好循環を作り出すのです。

成功する経営者の共通点
山田氏が関わってきた成功企業の経営者には、いくつかの共通点があります。まず、彼らは短期的な利益よりも長期的な成長を重視します。また、リスクを恐れず、計算されたリスクを取ることを厭いません。
さらに、成功する経営者は数字に強く、自社の財務状況を正確に把握しています。内部留保がどれくらいあり、それをどのように活用すれば最大の効果が得られるかを常に考えています。
一方で、失敗する経営者の多くは、感情的な判断をしがちです。「なんとなく不安だから貯めておこう」「税金を払いたくないから何か買おう」といった場当たり的な判断が、結果として会社の成長を阻害してしまいます。
■次回予告
第2回では、本書の核心である「エクストラ内部留保」について詳しく解説し、内部留保を「守り」の資金から「攻め」の資金に変える具体的な方法をご紹介します。実際の企業事例を交えながら、どのような投資が効果的なのか、どのようにリスクを管理すべきなのかを詳しく見ていきます。内部留保の新しい活用法に、きっと驚かれることでしょう。